【厳選】今すぐ旅に出たくなる本12選【ワクワクが止まらない】
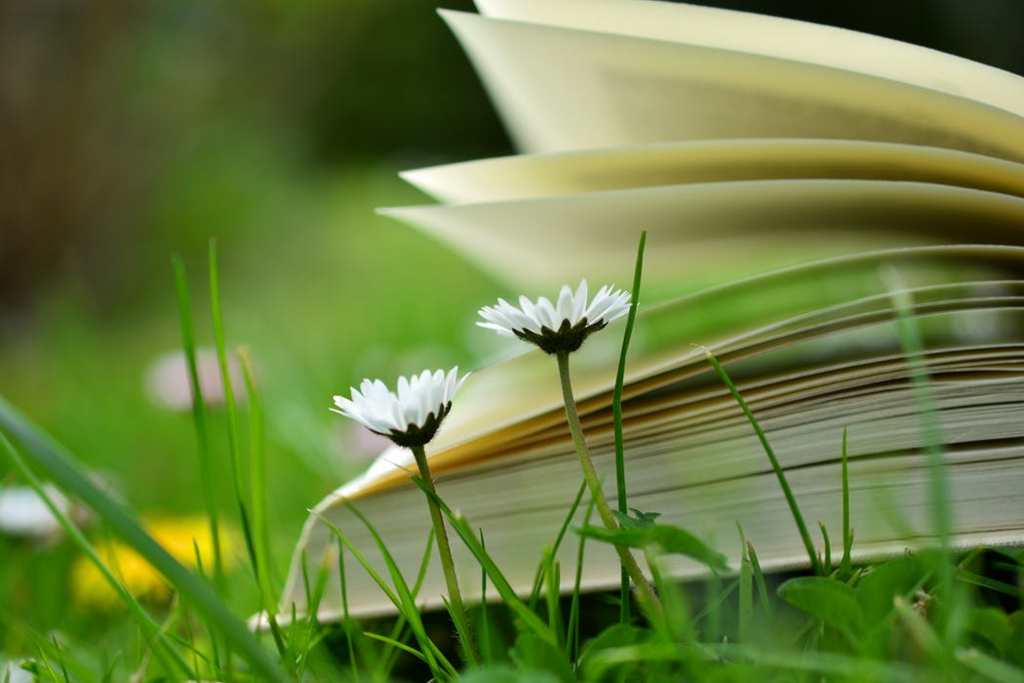
気づけば20代の一人旅で30か国を巡りました。
バスの中や空港や観光地の行列で、私はいつも本を読んでいたように思います。
本を開くことは新しい世界に出会うこと、それは旅ととても似ています。

ということで今回は、同じような旅好きに向けて
- 旅に出たくなるオススメ本
を、厳選して紹介したいと思います。
この記事にたどり着いた方にとって、新しい本との出会いがあれば、幸いです。
沢木耕太郎『深夜特急』
最初におすすめするのは、沢木耕太郎さんの『深夜特急』です。
まさに旅好きのバイブルといった作品。
これは文句なしで面白いので、誰もがオススメしたくなるのだと思います。
1巻から5巻までの薄い文庫本。
その中で、26歳の沢木さんが実際にユーラシア大陸を横断した際の旅の模様が記録されています。
この旅で、沢木さんが利用したのはバスだけ。
現代のようにスマートフォンなどない時代に。
沢木さんは旅で出会った人から聞いた情報、その場の出会いに身を任せて、香港~ロンドン間を旅します。
この本の魅力はなんといっても
- 沢木耕太郎氏の文章力にある
といっても過言ではないでしょう。
旅の記録を描いた本というのは、他にもあります。
しかし『深夜特急』ほど、瑞々しく異国の情景を描きながら、客観的に世界や他人を、何より若き発展の途上にある自分をみつめたルポルタージュは他にないでしょう。
その語り口は、頁をめくるこちらの手を決して休ませません。
思い切り手足が伸ばせる幸せを味わいながら、甲板に坐ってチャイを飲み、河を渡る風に吹かれていると、カトマンズからの三十時間に及ぶ強行軍が、もうすでに楽しかったものと思えてきそうになる。なんと心地よいのだろう。その気持ちを言い表したいのだが、どうしても適切な言葉が見つからない。
すると、放心したような表情で空を眺めていたアランがぽつりと言う。
“Breeze is nice.”
うまいなあ、と思う。
イギリス人なのだから、英語を上手に使うのに何の不思議はないけれど、それにしても、単純な単語を単純に並べただけのこの言葉の美しさはどうしたことだろう。
ブリーズ・イズ・ナイス。本当にそよ風は素敵なのだ。
まるで映画のワンシーンのような場面です。
沢木さんの文章は、読む人に見知らぬ土地への憧憬を掻き立てます。
最終章を読んでいるときは、沢木さんの旅が終わってしまうことが本当に惜しくて仕方ありませんでした。
後日談を収録した『旅する力』も、ぜひ併せて読むことをオススメします。
まだ読んだことのない方は絶対に必見、おすすめの一冊です。
植村直己『青春を山に賭けて』
次におすすめしたいのは、植村直己さんの『青春を山に賭けて』です。
植村直己さんは
- 世界初めて五大陸最高峰登頂した登山家
として、国民栄誉賞を授与されたことでも知られています。
ただ植村さんが登山家というより、根っからの「冒険家」であったことを知っている人は多くないのかもしれません。
かくいう私も、この本を読むまではそのような印象をもっていませんでした。
植村さんの凄い点は、あっぱれな行動力にあります。
ヨーロッパ山行まで、何年かかるかしれないが、とにかく日本を出ることだ。英語ができない、フランス語ができないなどといっていたら、一生外国などいけないのだ。
男は、一度は体をはって冒険をやるべきだ。
とにかく海外の山に登りたい。
語学はできない、金もない、ツテなど何もない。
それでも身一つで、日本を飛び出した若き植村さんです。
数々の機運に導かれるようにして、五大陸最高峰登頂を果たすのですが、本当に良くも悪くも成り行きまかせ。
何だかいい加減な感じがしますが、彼には絶対にこうするという強い意志があるんです。
誰も行ったことのない未開の地に足を運ぶという強い冒険心に基づく、確固たる意志。
それが強烈だな、と思いました。
人のやった後にやるのは意味はない。
それも人のためにではなく、自分のためにやるのだ。
[…]
私はきょうまで、ひとつひとつ強い決意のもとに全精神力を集中してやりむいてきたのだ。必ずやりぬける自信がある。
何が凄いって、植村さんは山に登るだけじゃないんです。
いかだでアマゾンの川下りをしたり。
南極大陸横断の夢を語っていたり。
「登山家」というよりも、もっと大きな枠組みで登山家を包括した「冒険家」として語られるべき人かな、と感じました。
前向きな植村さんの言葉は、読んでいて気持ちが良いものがあります。
海外好き、山好き、旅好き、冒険好きな方に、とてもおすすめな旅の本です。
星野道夫『旅をする木』
次に紹介するのは、写真家である星野道夫さんの
- 旅をする木
です。
これは、いい本です。
本棚にずっと置いておきたいな、と素直に思っている1冊です。
アラスカに恋するように旅に出て、厳しい自然と動物たちを写真に撮る日々。
そんな生と死が隣り合う暮らしの中で星野さんが綴った言葉は、胸にじんと染み入るものが多いです。
人の心は、深くて、そして不思議なほど浅いのだと思います。
きっと、その浅さで、人は生きてゆけるのでしょう。
ちなみに星野さんは、1996年のテレビ撮影中にヒグマに襲われて命を落とすことになりました。
それを知りながら、このエッセイを読むと人生の巡り合わせのようなものについて、考えさせられるものがあります。
高野秀行『恋するソマリア』
次に紹介するのは、高野秀行さんの
- 恋するソマリア
です。
高野さんの本は色々読んでいますが、これが一番好きでした。
ちなみにソマリアは世界最恐国として名高く、治安は最悪で観光客が最も少ない国といわれています。
高野さんはそんなソマリアに
- 超平和な地帯「ソマリランド」
があると聞いて、調査に出かけるんです。
その結果、ソマリアが好きで好きで仕方なくなった高野さんは
- 謎の独立国家ソマリランド
- 恋するソマリア(続編)
という二冊の本を出しました。
前作「謎の独立国家ソマリランド」も面白いのですが、少し長かったです。
どっちも読んだ方が、話の文脈はわかりやすいかも。
ちなみに高野さんいわく、異文化を知るのに大切なのは
- 音楽
- 料理
- 言語
の3つで、必ず現地の言葉を勉強して旅に出るのだそうです。
高野さんの冒険記は、どれも非常に男臭いんですよね。
でも、男に生まれていたらこういう旅をしてみたかった…と思うものもあります。
どの本を読んでもハズレがないので、ワクワクする旅のルポルタージュを探している人におすすめです。
前野ウルド浩太郎『バッタを倒しにアフリカへ』
次に紹介するのは、非常に読みやすいエッセイ本。
前野ウルド浩太郎さんの『バッタを倒しにアフリカへ 』です。
昆虫博士を目指す前野さんがアフリカ・モーリタニアに在外研究をされていたときの記録。
研究というと堅苦しい響きですが、めちゃくちゃ笑えます。
冒頭から、こんな感じです。
私はバッタアレルギーのため、バッタに触られるとじんましんが出て、ひどいかゆみに襲われる。そんなの普段の生活に支障はなさそうだが、あろうことかバッタを研究しているため、死活問題となっている。こんな奇病を患ったのも、14年間にわたりひたすらバッタを触り続けてきたのが原因だろう。
全身バッタまみれになったら、あまりの痒さで命を落としかねない。それでも自主的にバッタの群れに突撃したがるのは、自暴自棄になったからではない。
子どもの頃からの夢「バッタに食べられたい」を叶えるためなのだ。
前野さんは生粋のエンターテイナーという感じですね。
元々ブロガーとしてアフリカでの日々をブログにまとめていたそうです。
読み手の意欲と笑いを誘う文章が、非常にお上手。

▲前野さんのブログ「砂漠のリアルムシキング」にはこんな記事が載せられています。
アフリカのモーリタニアという国に関して、ここまで詳細に書かれているルポルタージュも希少だと思います。
ちなみにモーリタニアは
- 太っている女性がモテる
のだそうです。
妻が娘に吐くまで食べさせるのを止めに入ったら、離婚されてしまったという男性の驚き現地エピソードも書かれていました。
また、バッタを心から愛し、野心的に研究を進めていく前野さんの姿勢は、読んでいて非常に前向きな気持ちになれるものです。
ライトで読みやすくおすすめの一冊。
ただ、読むと笑ってしまいますので、外ではくれぐれもお気を付けください。
米原万里『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』
旅というより、本が好きな方に心からおすすめしたいノンフィクション本が
- 米原万里『嘘つきアーニャの真っ赤な真実 (角川文庫)』
です。
これは個人的に傑作だ、と思っています。
米原さんはロシア語の通訳として著名な方ですが、非常に文才にも恵まれている方なのだなと思いました。
1960年代に、子ども時代をチェコで過ごした米原さん。
その後に激動の時代を迎えた東欧で、音信不通になった3人の友人
- ギリシア人のリッツァ
- ルーマニア人のアーニャ
- ユーゴスラビア人のヤスミンカ
に再会するため、彼女は国境を越える旅に出ます。
回想録がメインとなるので、旅を疑似体験する本ではありません。
しかし、当時の複雑な社会状況を肌身で体験することができます。
かつ、小説としても見事な完成度をもって纏められた一冊として、この本は稀有だと思います。
私は、ベルリンの壁が崩壊した後に生まれました。
冷戦を同時代として生きていません。
そのため知らないことも多く、こういう本に出合うたび、自分の無知を痛感します。
まるでタイムトラベルのような臨場感があり、ページをめくる手が止まりませんでした。
素晴らしい読書体験を約束してくれる一冊だと心から思います。
小説ですが、同作者のこちらの本もおすすめです。
7. 村上春樹『辺境・近境』
次におすすめするのは、作家である村上春樹さんの
- 辺境・近境
というエッセイ本です。
村上春樹=小説というイメージをもつ人が多いと思いますが、実はエッセイの方が面白いのでは…と個人的には思うものがあります。
特に旅にまつわるエッセイが多いので、旅行のお供にぴったりなんですよね。
以前、ラオスに旅行に行ったときはこちらの本を読みました。
『辺境・近境』は90年代に書かれたエッセイで、国内無人島での少し滑稽な(?)サバイバル体験やメキシコ旅行の思い出などが書かれています。
変な話だとは思うのだけれど、ひとつものをなくすたびに、一度下痢をするたびに、僕の中にメキシコという国が一段しみこんでいくような気がした。冗談抜きで。ドイツにはドイツの疲弊があるし、インドにはインドの疲弊があるし、ニュージャージーにはニュージャージーの疲弊がある。でもメキシコの疲弊は、メキシコでしか得られない種類の疲弊なのだ。
香川でうどん巡りをした話も面白かった。
純粋に「こういう旅行したい」と思えるんですよね、紹介されていた「中村うどん」に機会があれば絶対来店したいと思いました。
軽快で読みやすく、小説よりクセがない。
それでいて、村上春樹ならではの語り口や視点がキラリと随所に光るという面白さもある。
手に取りやすく、旅好きにとっては面白さもお墨付きの1冊だと思います。
8. 片桐はいり『グアテマラの弟』
次に紹介するのは、役者である片桐はいりさんの
- グアテマラの弟
です。
タイトルの通り、グアテマラに住んでいる弟に会いに旅に出たときの思い出が語られています。
これは、めちゃくちゃ旅行したくなる本。
そして、すごくハッピーな気持ちになれるんです。
グアテマラに一人旅に出て、優雅に海外旅行して、冒険して…という感じではありません。
どこか覚束なく、頼りなく、旅慣れていない片桐さん。
だからこそ、彼女は周りに助けを求めるし、また彼女の人柄に惹かれるように人が集まってくる。
あたたかくて、やさしくて、とにかく明るい幸せな旅。
読後はまるで一編の映画を見たような気持ちになりました。
前作の『私のマトカ』もおすすめです。
9. 喜多川泰『「また、必ず会おう」と誰もが言った』
小説ですが
- 中学生
- 高校生
にぜひ読んでほしいのが、喜多川泰さんの『「また、必ず会おう」と誰もが言った。』です。
主人公は17歳。
生まれて初めての一人旅でヒッチハイクをしながら、東京から熊本に向かいます。
高校生といえば、学校が世界のすべてのように感じてしまう年頃です。
一人で家を出て、旅することのもつ意味。
それは大人にとっての旅行とは、全く異なる者だと思います。
私も十代のころ、青春十八きっぷで初めての国内一人旅をしました。

今でも旅行はスキです。
でも、あの旅行以上に達成感のある一人旅はないです。
沢木耕太郎さんも語っていましたが、旅は
- どこへ行くかよりもいつするか
に大きく左右されるのかもしれません。
喜多川泰さんの本は、非常に読みやすいです。
普段、本を全く読まない人にも読めると思いますし、誰の心も打つような普遍性があると思います。
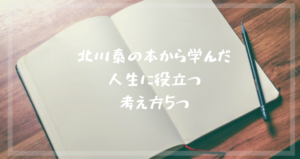
10. パウロ・コエーリョ『アルケミスト』
最後に紹介するのは、パウロ・コエーリョ『アルケミスト』です。
紹介する人があまりに多くて「何かの宗教本では?」と訝しんだほどに人気があります。
読んでみると、納得の内容でした。
例えるならば『星の王子さま』に近しい人生訓を主人公の旅を通じて得ることができる内容になっていると感じました。
私が一番心に響いたのは、老人が語るメッカの夢の話です。
いつまでもメッカに行こうとしない、夢であるはずなのにそれを叶えようとしない老人は、その理由をこのように語るのです。
メッカのことを思うことが、わしを生きながらえさせてくれるからさ、そのおかげでわしは、まったく同じ毎日をくり返していられるのだよ。たなに並ぶもの言わぬクリスタル、そして毎日あの同じひどいカフェでの昼食と夕食。
もしわしの夢が実現してしまったら、これから生きてゆく理由が、なくなってしまうのではないかとこわいんだよ。
おまえさんも羊とピラミッドのことを夢見ているね。でもおまえはわしとは違うんだ。なぜなら、おまえさんは夢を実現しようと思っているからね。わしはただメッカのことを夢見ていたいだけなのだ。
何かしたいことがある。
でも行動しない。
それは何故かというと、夢を夢のままにしておきたいから。
その通りだ、と頷いてしまうものがありました。
何か叶えたい夢がある、それなのに行動できない…
そんな方の心をぐっと前向きにしてくれる本として非常にオススメです。
まとめ|旅のお供に欠かせない「本」
ということで、以上10冊の本を紹介させていただきました。
本好きという視点からも、読みものとして十分に面白いと思えるものに限定したつもりです。
例えば石田ゆうすけさんの本も、旅したくなる本としては有名です。
こんな旅のスタイルがあるんだという面白さがあります。
ただ30分くらいで読めてしまうので、残念ながら読書体験という感じはあまりしない。
フィクションであれば宮本輝さんの『ドナウの旅人』もありますよね。
こちらは上下巻の分厚い小説。
私が宮本さんの小説が好きなので、個人的な好みにより過ぎかと考えて、今回はおすすめはしませんでした。
本にはやはり好みがありますし、人それぞれ読後の感想も異なるでしょう。
こういった記事で紹介することで一人でも多くの人が、新しい本と出会うきっかけになれば幸いです。
それでは、最後まで記事を読んでくださり、ありがとうございました!
今回の記事で紹介した本の一覧
本に関するほかの記事
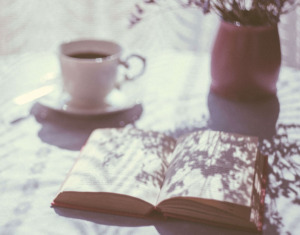





















コメント
コメント一覧 (2件)
森さん、私も米原万里『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』大好きです!
ベルリンの壁崩壊の時にすっかり大人だった私ならともかく、若い方がご紹介されていたので嬉しくなりました。
深夜特急も超愛読書です。旅好きは世代を超えますね(⋈◍>◡<◍)。✧♡
ru-funさん
コメント有難うございます!
米原万里さんの『噓つきアーニャの真っ赤な真実』本当に素晴らしいですよね。一人でも多くの人に読んでほしいと心から思いながら記事を書いていました。
本の魅力は世代を超えて、感想を共有できる点だとも思います。
同じような本好き&読書好きの方からご感想を頂けて、とても嬉しいです。
またいつもはてなスターを付けてくださり、感謝しています。
これからもよろしくお願いいたします。